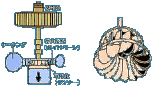渦巻きポンプを代用利用した密閉落差水圧水車、無改造では効率は少し低いが何といっても低コスト高回転です。
無変速直結です。
発電機は大き目が良いです。
フランシスの動翼(ランナー)です。

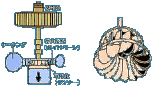

フランシス水車の映像です。

ペルトン水車バケットの映像です。

カプラン水車翼の映像です。

プロペラ水車は小型で出力が高く、
流れに設置もしやすいですね。
こんな製品も輸入されています。

超ミニ風力機器です。可愛いですね。
直径60mmでLED付きです。
(ブルーとグリーンLED)

ミニミニ風力発電機
ウインドクックです。
遊び心の楽しい機器です。

試作の小型ロングダクデットプロペラ水車の翼です。(翼径230mm/750W)

小型フランシス水車、受注製作品です。
落差により形態変化します。
15m以上の格差が必要です。

九州北部に設置してあります。
モニュメント用3連水車です。
低速水路では発電は難しいです。
発電しても微少発電です。
観光用の飾りですね。 |
風力発電と水力発電
ページは左の項目をクリックしてください。 |
* 大型機器は他励磁が多いですが小型機器は永久磁石発電機が主流です。
* 小型発電は、発電→三相整流制御→蓄電池→インバーターが基本構成です。
* 売電や自家節電の場合は適切なパワーコンデショナーを使用します。
* 風力は変動が大きいのでパワーコンの前に安定維持装置を設置します。
* いずれの場合も電圧などを検出しての自動作動安全制限装置を設置します。
* 動力の変速比は少ないほうが効率が高く、遊星ギヤは効率がよいです。
* 動力源能力を超える定格電流の発電機選択が効率アップのひとつの要素です。
* 自然エネルギー発電は効率アップ、低コスト、安全、メンテナンスが重要です。
* モニュメントなどの飾り物の水車風車もあり、それはそれで意義はありますが、
やはり有効に発電してしっかり役立てたいですね。実用コストも重要です。
* 風力発電カタログは全く信頼のできない誤計算品があまりにも多く見られます。
適切に正しく計算してほしく思います。誇大な想像希望出力表示は止めましょう。
外観ばかり大げさで低効率高コストで出力がミニミニという風水力も多いです。
電力は発電機で決まるのではなく動力源能力で決まるのです。誤解が多いです。
* 発電機は力学回転動力→電気出力にする変換機器なのです。
そして発電した電力は安全に安定化しなければ使い物になりません。制御です。
* 制御装置は安全制限回路プラスMPPT制御が最新最良です。
* 設備稼働利用率は水力が最高、次は地熱、3番は良い地域の風力や太陽電池です。
** 風力発電 **
風力発電は強風時の出力よりも設置地域に適合した翼型や出力特性が重要です。
理論的には風速とエネルギーは3乗に変化します。ですが現実の風は少し異なり多くの条件を考慮します。
また、弱い風でも回転しているから発電していると安心してはいけません。なぜなら目標電圧に達していなければ全く役にたたないからです。起動風速が低いのはメリットですが実用数値が重要です。
分かりやすく小型の独立型12V鉛蓄電池使用でいいますと、鉛蓄電池の充電完了電圧14.6V+制御電圧0.1Vから3V(機器により異なります)を波形最大値が超えなければ無負荷の空運転だということです。
プロペラタイプの風車には強風タイプと弱風タイプがあり、
最大出力数字は強風タイプが大きいですが、陸上の実用性は弱風タイプが上です。
例えば枚数が少ないと効率は上がるが強風用となり径とアスペクト比の極めて大きい翼になり小型では利用しにくくなります。
枚数が多いと最高効率点が低風側になりトルクも稼げて小型では優良な風力発電機になります。
私の試作機では広翼6枚や普通翼10枚の128〜138cm径クラスで、風速5m/sにて100Wを超えました。
そして風速10m/sでは約1000W近くに達しました。
強風時は高回転になり電圧が異常にあがり、遠心力も増大します。
だからといって完全停止が必ずしも安全とはいえません。なぜなら抗力が最大になるからです。
完全停止にする場合は抗力を少なくするような方法をとります。フェザリングや偏向などもその方法です。
翼の安全設計は基本強度と疲労強度、弾性強度そしてバランスともうひとつ破損したときの安全性です。
発電制動の一種である短絡制動は小型風力機器に採用されており強風状態と使用時間などに留意すれば問題は少ないですが、限界を越えて大事な発電機を焼損される方も多くおります。
発電機をゆとりあるランクにして転換負荷制御をするのが小型機の比較的安全な電気制動です。
高性能なのは安全制限装置プラスMPPT制御です。安全装置が要点です。
風力発電機器の設計には単純な機械電気知識だけでなく大幅な変動電気(電圧電流だけでなく周波数も)と交流直流と蓄電池特性と流体工学、その上に安全設計と管理があります。
野鳥など動物を含めた自然環境にも十分な配慮が必要です。
風車にはプロペラタイプ以外もあります。垂直軸型と呼ばれているタイプです。
(水平ダリウスもありますので垂直軸型という表現は必ずしも正しいわけではありませんが一般化しています)
揚力型と抗力型があり、抗力型などは低効率高コストで発電力よりモニュメント性が高くなります。
揚力型ではダリウスやジャイロミルがありますが起動力がとても小さく実用性に乏しいです。
垂直軸風車は揚力と抗力の両方を上手に利用する設計ですと効率も上がり実用になります。
縦軸風車のメリットは安全性や静粛性でしょう。住宅地でも使用できる風力発電機です。
街路灯や道路標示にも縦軸風車は安全で有望です。
基本特性はプロペラタイプが効率も回転数もトップです。
2枚3枚翼が効率や回転数で有利ですが、翼の枚数が増加すると直径が小さく出来て最高効率点が低風域になりトルクがあがり小型ではとても実用的な風車になります。
大きめの風力発電機器はオートピッチコントロールにするのがベターです。
地域風況によってはスリップリングは無くても問題発生しないことも多いです。
** 水力発電 **
水力の基本は落差と水量です。
毎秒10リットル落差10mの水のパワー(水の運動エネルギー)が980Wです。
でもそれを全てエネルギーに変換はできません。
水力はできる限りスムースに圧水を流入させますが、特に重要なのはいかに速く排水させるかです。
落差タイプの水圧配管内はキャビテーションの無い満水圧移動です。
単純流水ではありません。無気泡でランナーまで満水圧なので効率が高いのです。
小型の発電としては水力はとても魅力的な発電です。設備稼働利用率はトップクラスです。
小型でも十分な安定連続した発電電力が得られます。(安定連続が大きな要素です)
河川法や水利権などの規制があり、今後の規制緩和を望みます。
高落差水車にはフランシスやペルトンがあります。密閉水圧水車です。
日本の大型水力発電のほとんどはフランシス型で効率も高いです。
ペルトン水車は高速放水の衝突位置関係と合理的跳ね返りでエネルギー吸収し手前の羽根が邪魔にならないような工夫がされています。ターゴ水車はペルトンと似ていますが斜め放水です。
プロペラ水車(カプラン水車を含む)は低落差から、そして小から大水量で利用でき効率もとても良いです。
落差水圧タイプと流水タイプはプロペラの設計が全く異なります。
マイクロ水力では有望のトップ水車です。特にダクデットプロペラ水車やクロスフロー水車が候補です。
クロスフロー水車は製作コストも少なく低落差でも効率を高くできます。
落差がとても大きいならペルトンやターゴも良いでしょう。
  
落差水圧型は小型でも出力は大きく、流水型は大型でも低出力です。
古くからの開放外輪型では下掛けや胸掛けもありますが上掛け胸掛けが効率が高く、
下掛けは低効率で出力のわりに大きくなります。
極低速回転ですから回転数アップの変速機械損失も大きくなります。
下掛け等、水流発電の水車動力計算は水流圧を動圧として計算します。水をせき止めては出力が無くなりますから排出効果を良くして動力を取り出します。
また水は密度が高いので高強度で錆に強く製作する必要があります。
螺旋(スパイラル)水車は微少落差水流ではとても低効率ですが斜水路【30°以上】で設置角度が大きくなると水の質量利用ができ実用になります。
なぜ低性能か? 流体にネジは効かず、ダ・ビンチのヘリコプターは空を飛べません。
プロペラのようにネジではなく揚力と迎え角が重要です。
水流回転では一周目以降は邪魔者になり長いと尚更に効率が低下します。
** 大昔からラセン水車と下掛け水車が極低効率なのはプロの常識です。
** ビギナーの方へ小型発電と電力測定 **
** 発電電力を気にする前に現地の水力を調査考察するのが最重要です。
小型発電は設置コストが低く融通性が高く環境負荷が小さいです。
大き目の発電設備をしても有効利用消費をしなければ見かけの発電設備容量があるだけです。
発電機器の効率をよくすることも必要ですが、可動利用効率を上げるのは特に重要です。
300W〜500Wというと小さく感じるかも知れませんね、でも家庭の2K3K契約の平均消費電力は330W前後なのです。
太陽光発電5KW設備の平均売電量は570W前後なのです。夜や雨も曇りあり、これが現実の数字なのです。
カタログなどの最大出力という見かけの数字に惑わされず、的確に運用事実を見るようにしましょう。
発電出力能力試験 と 発電利用運用、 とは全く別物で接続機器も測定方法も異なります。
それらをよく理解しましょう。試験測定方法も誤解されている方がとても多いです。
回転して電圧発生しても電流を流さなければ発電力はゼロです。有効消費してこそ発電力です。
波高値電圧は交流実効値x1.414倍、三相電力は1相実効値電圧x相電流x1.732倍です。
******************************************************************************************
動力としての風車はプロペラタイプやそれに類似した型が主流です。
下の映像は右が6〜8m級の風力発電機製作現場、左(電力システム工学より)が風車の基礎特性です。
現実風の風力機器はプロペラタイプ以外は出力が思ったよりずっと小さいのが実情です。
設置地域の条件で適切な計算と計画、安全とメンテナンス性を考えて的確な設計しましょう。 |
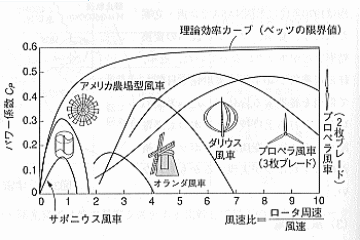  |
 
 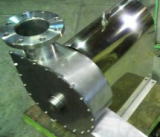
水力発電システム、風力発電システム、各部品を販売しております。
各種発電機と三相整流システムや各種制御装置など、お気軽に御連絡をください。
各種の低消費電力LED投光照明機器なども扱っております。
御問合せはワンコのとなりのメールマークをクリックしてください。
コンサル解説に出張もしております。
各種製作します。発電機、部品は標準品から安価品特価品もございます。
よろしく御願い申し上げます。
Eメールはこちらです。↓
(電機電子力学、工学コンサル)  
(有)Eテク・ワタナベ 渡邊
TEL 0166−62−7039
FAX 0166−62−7249
チーム・マイナス6%に参加しています。
 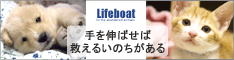 |
|
|